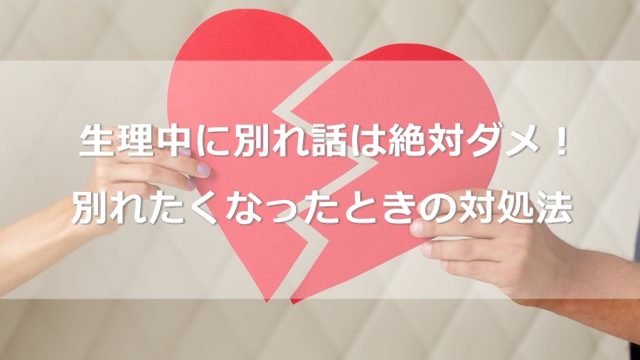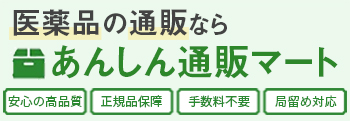月に10~15%の体重が減るダイエットを実施してしまうと、生理が遅れたり止まってしまいます。
これは脳が「緊急事態」を感知していることから引き起こされる現象として知られています。
今回の記事では、ダイエットと生理周期の関係性についてご紹介します。
急激なダイエットによる体重減少は生理が遅れる・止まる原因になる
急激なダイエットで体重が一気に減ると、生理が不規則になったり、完全に止まってしまうことがあります。
これは単に「痩せたから生理が来ない」という単純な話ではなく、体が危機的なエネルギー不足状態にあると脳が判断し、妊娠や出産といった生殖機能を一時的にシャットダウンするためです。
つまり、生理が止まるのは「痩せすぎの副作用」ではなく、体が命を守るためにとった防衛反応なのです。
脳は生命維持を優先し、生殖機能を一時停止する
体に十分な栄養が届かなくなると、脳の視床下部は今は妊娠に適さないと判断します。
その結果、排卵を促すホルモン(GnRHやLH・FSH)の分泌が減り、卵巣からのエストロゲン産生も低下します。
これにより排卵が止まり、月経が来なくなるという仕組みです。
これは一種のサバイバルモードであり、「妊娠よりもまず生き延びることを優先する」という本能的なメカニズムが働いています。
スポーツ選手に月経異常が多いのも同じ仕組み
アスリートやダンサーにおいて、月経異常(無月経)は一般女性よりも明らかに高頻度で見られています。
一般女性では2〜5%程度なのに対し、運動習慣のある女性では5〜25%、特にバレエや持久系スポーツなど「審美性が重視される競技」では最大で69%にのぼることが報告されています。
これらのデータは、スポーツやダンスの種類や強度、身体的プレッシャーによって月経への影響が大きく異なることを示しています。
見た目には筋肉質で健康そのものに見える人でも、実際にはエネルギー収支がマイナスになっており、脳が生殖機能を一時的に停止させているケースが多くあります。
これは「視床下部性無月経」と呼ばれ、無理なダイエットによる生理停止と本質的には同じメカニズムで起こっています。
| 項目 | 一般女性 | 運動習慣のある女性 | 審美・持久系アスリート |
|---|---|---|---|
| 無月経の発生率 | 約2〜5% | 約5〜25% | 最大69% |
| 原因 | 強いストレス、栄養不足など | 運動によるエネルギー消費過多 | 厳しい体重管理・審美プレッシャー |
| 該当例 | 無理なダイエット中の女性など | ジム通い、ランナー、部活動 | バレエダンサー、フィギュア選手、陸上長距離など |
| 特徴 | ホルモンバランスの一時的な乱れ | 運動量と摂取カロリーの不均衡 | 視床下部性無月経のリスクが高い |
生理が遅れる・止まってしまうダイエットの基準
単に体重を減らすことが問題なのではなく、「栄養不足の状態が続いているかどうか」が、生理に影響するかどうかの判断基準になります。
自覚のないまま、身体が危険信号を発しているケースも多いため、以下の3つの指標に注意しましょう。
- EA(エネルギー利用可能量):30kcal/kgを下回ると高リスク
- 体重減少率:月に10〜15%の減少は危険
- BMI:18.5以下は要注意
EA(エネルギー利用可能量):30kcal/kgを下回ると高リスク
EA(エネルギー利用可能量)は、摂取カロリーから運動で消費される分を引いた「体に残るエネルギー」のことです。
体重1kgあたり30kcalを下回ると、体の機能維持に必要なエネルギーが不足し、生殖機能を停止するリスクが高くなります。
ハードな運動をしているのに「そんなに食べてない人」は、知らずにこのラインを下回っている可能性があります。
| 区分 | EA(kcal/kg FFM/day) | 解説 |
|---|---|---|
| 安全帯 | 45 kcal/kg FFM/day 以上 | 運動量とエネルギー消費がバランスされ、月経・骨の健康など生理機能が維持されやすい。([turn0search8], [turn0search10]) |
| 注意帯(要注意) | 30‑45 kcal/kg FFM/day | 微妙に不足気味な状態。月経障害などのリスクが徐々に高まり得る「サブクリニカル」エリア。([turn0search10], [turn0search12]) |
| 危険帯(低EA) | 30 kcal/kg FFM/day 未満 | 臨床的に再生機能や骨代謝などが影響を受けるリスク。LHのパルス分泌低下、月経停止なども。([turn0search3], [turn0search11], [turn0search12]) |
あなたの「EA」を計算してみよう
以下の手順で、自分がエネルギー不足に陥っていないかを簡単にチェックできます。
- 1日の摂取カロリーを把握する
- 1日の運動で消費したカロリーを調べる
- 体重と体脂肪率から「除脂肪体重(FFM)」を出す
- 下記の式でEAを計算
EA(kcal/kg) =(摂取カロリー − 運動消費カロリー) ÷ 除脂肪体重(kg)
例)体重50kg、体脂肪率20%、摂取カロリー2,000kcal、運動消費600kcalの場合
除脂肪体重 = 50kg ×(100 − 20)÷ 100 = 40kg
EA =(2000 − 600)÷ 40 = 35 kcal/kg
体重減少率:月に10〜15%の減少は危険
急激な体重減少は、体にとって強いストレス刺激となり、ホルモン分泌に深刻な影響を及ぼします。
脳の視床下部はこの変化を非常事態と判断し、エネルギーの浪費を防ぐために、生殖機能や甲状腺の働きを抑えるよう指令を出します。
その結果、エストロゲンの分泌が急激に低下し、月経が止まる・遅れるといった異常が起こりやすくなるのです。
目安として、1ヵ月の体重減少が10%以上に達すると、視床下部性無月経などのリスクが急上昇します。
特に体脂肪が減る速度が速いほど、ホルモンバランスの崩れは顕著になります。
たとえば、体重50kgの人が1ヵ月で5kg落とせば10%、7.5kgで15%に達します。
このスピードでの減量は、体にとって飢餓状態と同じと見なされ、妊娠機能を停止させてでも省エネモードへ移行しようとします。
減量の成果に満足しても、ホルモンや代謝が崩れていると、生理だけでなく免疫力・筋量・骨密度にも悪影響が及ぶため注意が必要です。
BMI:18.5以下は要注意
BMIが18.5を下回ると、日本肥満学会やWHOの基準でも「低体重(やせ型)」と分類され、健康障害のリスクが高いとされています。
この状態では、体脂肪率が15〜20%程度まで落ち込むことも多く、女性ホルモンのバランスに重大な影響を及ぼします。
特に女性にとって重要なホルモンであるエストロゲンは、卵巣だけでなく脂肪組織からも分泌されています。
脂肪が少なすぎると、ホルモンの材料が不足するうえ、体が「妊娠に適さない状態」と判断し、視床下部や下垂体の働きも鈍化します。
その結果、排卵が停止したり、無月経や月経不順が起こるケースが多くなります。
痩せていても見た目がスリムでも、「脂肪が足りない」ことは生理の維持にとって明らかなリスクです。
体脂肪率が18%を下回ると、月経異常の頻度が一気に上がるとする報告もあり、BMIだけでなく脂肪量の目安も意識することが重要です。
ダイエットで生理が止まってしまった、遅れる場合の対処法
生理が2ヶ月以上遅れていたり、完全に止まってしまっている場合は、単なるダイエットの影響と片付けず、体を守るための対処が必要です。
放置すると将来的な不妊リスクや骨粗しょう症にもつながる可能性があるため、以下の方法で改善を目指しましょう。
- 正しい食事で摂取カロリーを増やす
- 睡眠・ストレスを管理する
- 3ヵ月以上生理が来ない場合は病院でホルモン療法を受ける
正しい食事で摂取カロリーを増やす
生理を取り戻すためには、まず慢性的なエネルギー不足を解消することが最優先です。
1日3食を抜かずに食べ、主食(糖質)、主菜(たんぱく質)、副菜(ビタミン・ミネラル)をバランスよくそろえることが基本となります。
特に意識したいのが「脂質」と「たんぱく質」です。
脂質はホルモン合成の原料であり、卵巣からのエストロゲン分泌にも深く関わっています。
「太るのが怖い」と油や脂肪を極端に避けると、女性ホルモンが作られず、排卵が再開しない原因にもなります。
オリーブオイルやナッツ類、青魚などから良質な脂質を取り入れることが大切です。
また、たんぱく質はホルモンの構造そのものにも関与し、筋肉・血液・酵素・免疫など体の修復にも欠かせません。
体重1kgあたり1.2〜1.5g程度を目安に、肉・魚・卵・大豆製品などから毎食こまめに補いましょう。
「カロリー」ではなく「栄養」で体を満たすことが、生理を取り戻すための第一歩です。
睡眠・ストレスを管理する
睡眠不足や慢性的なストレスは、視床下部の機能を低下させ、ホルモンの分泌バランスをさらに崩す原因になります。
特にGnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)の分泌が不安定になると、排卵や月経周期にも直接的な影響を及ぼします。
夜更かしや不規則な生活、体型への焦りなどの心理的ストレスも、脳にとっては「妊娠に適さない環境」として認識されやすく、無月経のリスクを高めるのです。
まずは1日7〜8時間の質の良い睡眠を確保し、毎日同じ時間に寝起きする“体内時計のリセット”を意識しましょう。
また、ストレス軽減のために、次のようなリラックス習慣を取り入れるのがおすすめです:
- ぬるめのお湯で10〜15分の入浴(副交感神経を優位に)
- 寝る1時間前のスマホ・PCの使用を控える(ブルーライト遮断)
- アロマ・深呼吸・日記など、自分だけの「癒しルーティン」
体の機能は心の状態と密接に関係しています。
「頑張らないことを頑張る」くらいの気持ちで、心身の休息を優先しましょう。
3ヵ月以上生理が来ない場合は病院でホルモン療法を受ける
3ヵ月以上生理が来ていない場合は、「続発性無月経」と診断される可能性があります。
この状態が長引くと、将来的な妊娠への影響や骨密度の低下なども懸念されるため、婦人科の受診が必要です。
血液検査によるホルモンの状態チェックと、必要に応じて低用量ピルやホルモン補充療法が行われます。
保険適用での治療も可能なケースが多く、費用は月数千円〜が一般的です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処方されるピルの種類 | 混合型経口避妊薬(エストロゲン+プロゲスチン) |
| 代表ブランド | ファボワール28錠、ラベルフィーユ28錠、マーベロン28、トリキュラー28、アンジュ28錠など |
| 1ヶ月の費用目安 | 約2,000~3,500円(ピル本体)+診察・検査費 計 約3,000〜5,000円/月 |
| オンライン診療の特徴 | 初回診察+処方が可能で、オンライン専用プランにより月々の負担を軽減できる |
健康的な減量ペースを守れば生理もダイエットも両立できる
生理が止まるほどの過度なダイエットは、短期的な成果を得られたとしても、長い目で見ると健康と美の両方を損なうリスクがあります。
月に体重の5%以内のゆるやかな減量を目安にし、栄養・運動・睡眠のバランスを保ちながら取り組むことが大切です。
生理は「健康状態のバロメーター」であり、乱れたときには体が教えてくれているサインです。
その声を無視せず、丁寧に応えることが、リバウンドしない、芯からキレイなダイエット成功への近道になります。
この記事の参考サイト参考サイト
Functional hypothalamic amenorrhea:wikipedia
スポーツ栄養における「エネルギー不足」の概念とその生理的影響
女性アスリートの利用可能エネルギー不足アセスメントツールの開発と妥当性の検討
BMIとは何ですか?:TANITA
ピルの種類:ジャスミンレディースクリニック